- 親が一人暮らしで心配だが、なかなか様子を見に行けない…
- 引っ越すわけにもいかないし、どうしたらよいかわからない…
- 見守りサービスって色々あるけど、何を選んだらいいんだろう…
遠方に親が住んでいるとこのような悩みが生じますよね。
様子を見に行きたいけど、平日は仕事が忙しく、休日は家庭のことをやっているとなかなか時間を確保できません。
そんな状況でも、「見守り」が適切に出来ないと様々なリスクに繋がります。
この記事では遠方に高齢な一人暮らしの親を持つ方に向けて、おすすめの見守り方法の選び方について紹介します。
この記事を通して、自分の状況にあった見守り方法を見つけて、
見守る側・見守られる側の双方が安心して過ごせる見守り計画を立てていきましょう。
- 遠方の親の見守り方法として、訪問・同居・見守りサービスの利用などが挙げられる。
- 見守りサービスは訪問型・宅配型・緊急時駆けつけ型など多様な選択肢がある。
- 見守りサービスの導入時には、見守られる側の意見を尊重し、最適なサービス・グッズを選ぶことが大切だと考えられている。
- コスト・利便性・設置の簡単さなどを考慮し、自分の環境に合った見守り方法を検討してください。
この記事を書いた人
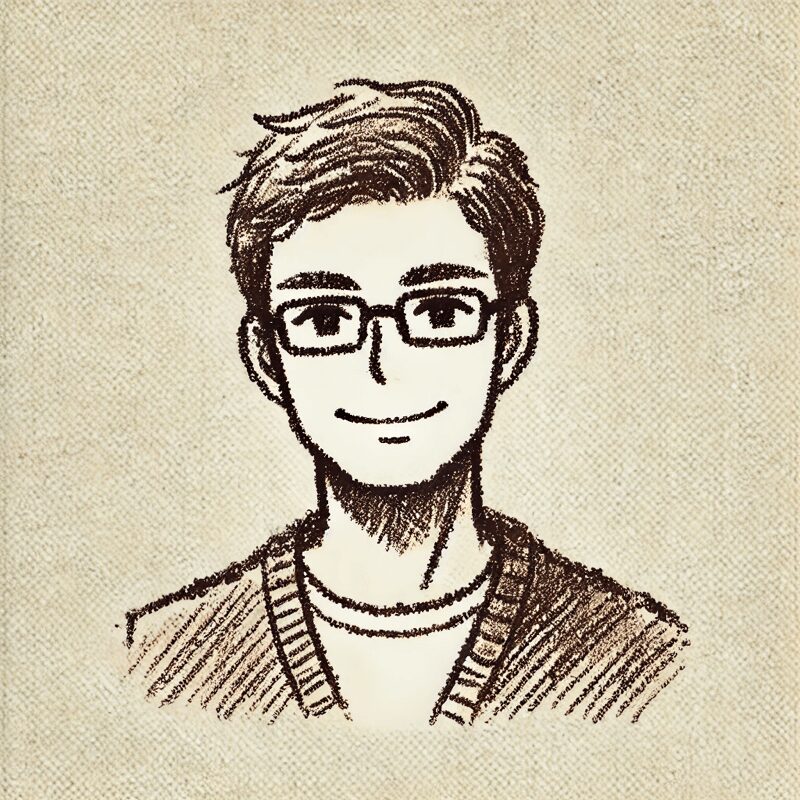
ロキ
30代の会社員。
数年前、祖母が亡くなり一人暮らしになった祖父をサポートをする中で、疲弊する母の姿を見て、「どうにかできないか…」と考えるように。
そこで出会ったのが「高齢者の見守りサービス」でした。
このサービスをもっと多くの人に知ってもらい、「離れていても親を見守る方法」を発信したいと思い、このブログを運営しています。
ぜひ参考にしていただき、少しでもご家族の負担を減らし、安心できる生活につなげていただければ嬉しいです。
日本の高齢者の生活実態

日本の高齢者人口
近年、日本では高齢化が進んでいます。
総務省の統計によると、2023年時点で65歳以上の高齢者は日本の総人口の約30%とされており、
そのうちの一人暮らしの人口は約40%にもなるとされています。
(参考:総務省「統計からみた我が国の高齢者-「敬老の日」にちなんで-、内閣府「令和3年版高齢社会白書(全体版)」一人暮らしの高齢者世帯数・65歳以上人口に占める割合)
このようなデータから、家族による見守りの重要性が浮き彫りになっています。
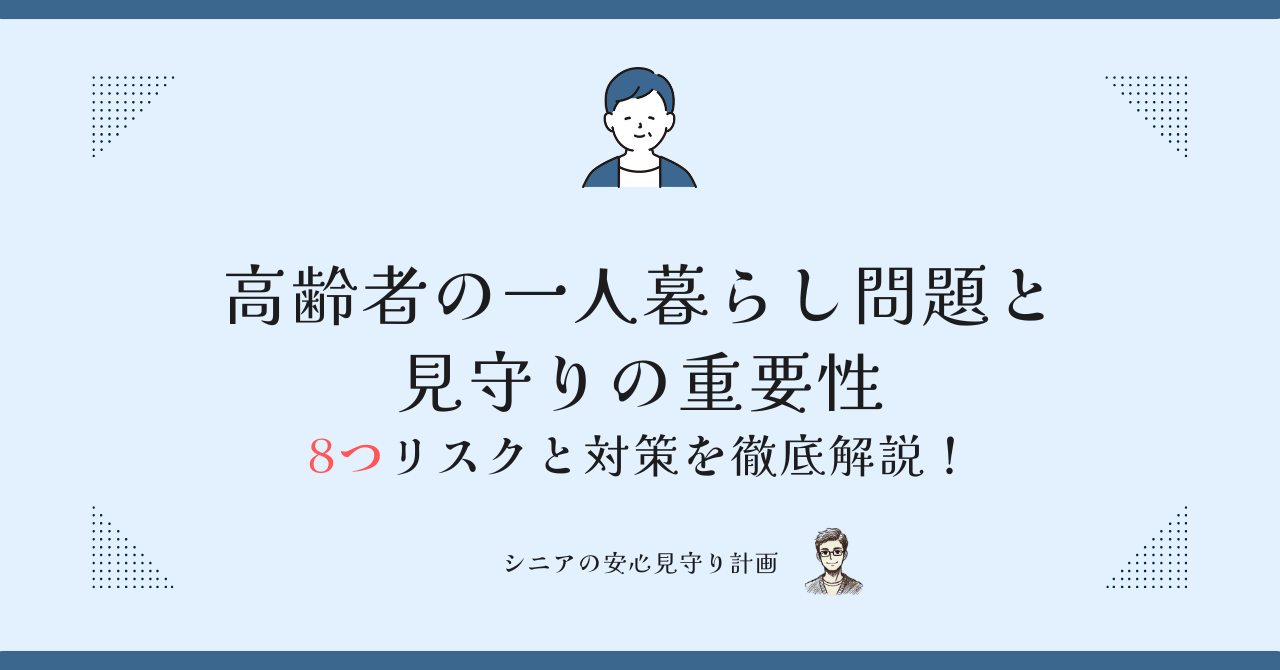
近くに家族がいない高齢者の人口

issin株式会社が行った調査によると、調査対象の約7割(65.2%)が65歳以上の「高齢者の親」がいると回答しています。
その7割の回答者のうち、約3割(28.5%)が、直近の夏のお休みには親に会うことが出来なかったと回答しています。
現代人は仕事も多忙な方が多く、なかなか帰省が出来ないという方も多いことがわかります。
また、リモート技術が発達し、電話やビデオ通話などで済ましてしまう方も多いのかもしれません。
(参考元:issin株式会社「高齢の親の健康と生活に関する調査」)
遠方の親の見守りが必要な方が抱える悩みとは?
issin株式会社が行った調査の中で、「親のこと」で気がかりなことについての質問がされており、
下記のような回答結果が得られています。
| 回答結果 | 割合 |
|---|---|
| 健康状態 | 27.0% |
| 介護が必要になる可能性 | 16.0% |
| 認知症の兆候・認知機能の低下 | 14.6% |
| 実家や掃除の片付け | 8.3% |
| 詐欺対策や防犯 | 8.2% |
| 財産管理 | 5.7% |
| 精神的なストレスや鬱 | 5.6% |
| 孤独感や孤立感 | 5.1% |
| 適切に社会活動や交流があるか | 5.0% |
この調査結果からも、健康や介護についての心配をされている方が多いことがわかります。
遠方で暮らす親の見守りはどうするべき?

先ほど紹介した統計データからもわかるように、親が一人暮らししている状況においては、家族の見守りが重要となり、同時に大きな課題となります。
ここでは遠方で暮らす親の見守りをどのようにするべきかを解説していきます。
定期的に訪問する

ひとつは家族が定期的に訪問することです。
ただ、どうしても遠方の場合には見守りする側の負担も大きくなるので、頻度を増やすことは難しい場合があります。
見守られる側の親の状態次第ではありますが、電話やチャットを交えたり、兄弟がいる場合はローテーションしながら週1回〜月1回程度は訪問するようにしましょう。
近くに引っ越してもらうor同居する

近くに引っ越してもらうことも手段の一つです。
ただ、長く持ち家に住んでおり住環境を変えることが大きなストレスになることも考えれるので、
ご本人としっかりと話し合いをして決める必要があります。
また、持ち家から引っ越して売却などをする場合はその分色々な手続き等が発生するので、
見守られる側への負担も大きくなります。
同居する場合は、自分の家族の協力が必要になりますし、自分の子どもの家に入り込むのは少し気を使う…。という方もいらっしゃるので、しっかりと話し合いをし、お互いに納得の上で進めることが重要です。
見守りサービス・グッズを利用する

私は見守りサービス・グッズを利用することをおすすめしています。
民間で行っているものや、自治体で行っているもので様々なサービス・グッズがあるので、状況に合わせて利用することができます。
導入費用も低価格で済むものもありますので、まず見守り体制を作るという入口の段階では良い選択になるのではないかと考えています。
どのようなサービスがあるかは後ほどまとめてご紹介させていただきます。
訪問・通所介護サービスを利用する

要介護認定を受けている方であれば、訪問介護やデイサービスなどの利用をすることも手段の一つです。
訪問介護はご自宅でケアを受けることが出来ますし、デイサービスは自宅まで送迎してくれるので、
なにかあった際にも早期に気づくことができます。
ただ、自分はまだ介護サービスなんて利用したくないという高齢者の方も一定いらっしゃいますので、ご本人のご意向を尊重しながら検討してもらえればと思います。
高齢者施設に入居してもらう

高齢者施設に入居してもらうことも手段の一つです。
いわゆる老人ホームのイメージとは少し違った、サービス付き高齢者向け住宅であれば要介護認定を受けていない方でも入居することができます。
ただ、費用が他の選択肢よりも高額になるため個人的には他の手段で見守り体制を作ってみることをおすすめします。
見守りサービス・グッズとは?
見守りサービス・グッズはどのようなものがあるかをご紹介します。
サービスとグッズで8つの分類に分かれるのでそれぞれの概要を理解して、皆さんの状況を考えるとどのようなものを選べば良いかという観点で読んでみていただければと思います。
訪問型の見守りサービス
ヤマト運輸の「クロネコ見守りサービス」や、郵便局の「みまもりサービス」などが該当します。
| 特徴 | |
| 配達員や郵便局員が定期的に訪問し、高齢者の様子を確認してくれます。 確認結果を家族に報告してくれるサービスです。 | |
| メリット | デメリット |
| 直接対面での確認が可能で、異変などを発見しやすい。 配達と組み合わせるため、比較的低コストで導入が出来る。 高齢者とのコミュニケーション機会を増やすことが出来る。 | 訪問頻度が週1回程度と少ないため、緊急時の対応には不向き 高齢者のプライバシーを気にする場合がある。 サービス提供エリアが限られていることがある。 |
宅配型の見守りサービス
「ワタミの宅食」や「ヤクルト届けてネット」などの飲食物を宅配してくれるサービスが該当します。
| 特徴 | |
| 配色サービスと見守りを組み合わせたサービス 配達員が手渡しで食事を届ける際に安否確認を実施してくれます。 異変時の連絡については企業によって異なります。 | |
| メリット | デメリット |
| 毎日訪問するため、変化に気づきやすい。 高齢者の栄養管理が出来る。 食事を通じて自然な見守りが出来る。 | 直接的な健康チェックや医療的なサポートはできない。 配達時間が決まっており、24時間対応ではない。 食事の選択肢が限られることがある。 |
電話・アプリ型の見守りサービス
「見まもっTEL」や「みん歩計」などが該当します。
| 特徴 | |
| 定期的な電話やアプリ通知で安否確認を行える。 AIやオペレーターが会話を行い、異変を察知してくれます。 スマートフォンや固定電話を活用するので、導入しやすいです。 | |
| メリット | デメリット |
| 全国どこでも利用が可能。 導入コストが低く、手軽に始められる。 アプリであれば高齢者が外出中でも確認できる。 | 固定電話の場合、高齢者が外出中だと確認ができない。 認知症の方には向かない場合がある。 緊急時の即時対応が難しい |
警備会社・緊急時駆けつけ型の見守りサービス
「セコム」や「ALSOK」などの大手警備会社が提供しているサービスです。
| 特徴 | |
| 高齢者が緊急ボタンを押すと警備員が駆けつけしてくれます。 センサーやカメラと組み合わせたシステムもあるので安心の見守り体制です。 24時間対応のサービスが多く、安心。 | |
| メリット | デメリット |
| 緊急時の対応が迅速で安心感がある。 センサーなどを活用すれば、異変を自動検知できる。 警備会社ならではの安心感 | 月額費用が比較的高額(数千円〜1万円以上) ボタンを押さないと発見が遅れてしまう可能性がある。 サービス内容によっては、過信しすぎてしまうリスクも。 |
センサー型の見守りグッズ
「アイシル」や「au簡単見守りプラグ」などが該当します。
| 特徴 | |
| ドアの開閉や人の動きを感知し、異常を検出してくれます。 異常時に家族へ通知する仕組みです。 温度や湿度センサーを搭載した製品もある。 | |
| メリット | デメリット |
| 非接触で見守れるため、高齢者の負担が少ない 24時間の見守りが可能 プライバシーを守りながら安否確認が出来る | 一定の行動パターンがないと誤検知の可能性がある。 初期導入コストがかかる・ ネット環境が必要なものが多い。 |
カメラ型の見守りグッズ
「MANOMA親見守りセット」や「みまもりCUBE」などが該当します。
| 特徴 | |
| 室内に設置したカメラでリアルタイムで見守りが出来る。 スマホアプリで遠隔確認が可能。 音声通話機能付きのものもある。 | |
| メリット | デメリット |
| 高齢者の状況をリアルタイムで把握できる。 緊急時の対応が迅速になる 音声機能付きならコミュニケーションも取れる | プライバシーの問題(監視されていると感じる) ネット環境が必要 設置場所に注意が必要 |
ロボット型の見守りグッズ
「BOCCO emo」や「GROOVE X LOVOT」などが該当します。
| 特徴 | |
| コミュニケーションロボットが高齢者と会話 音声やアプリでの見守り機能を搭載 AIによる対話や自動通知機能がある。 | |
| メリット | デメリット |
| 高齢者の孤独感を軽減出来る かわいらしいデザインで心理的負担が少ない 家族とのメッセージ送受信ができる | 初期費用が高い(数万円〜数十万円) AIの精度に限界がある 物理的なケアは出来ない |
家電型の見守りグッズ
「象印みまもりホットライン」や「Hello Light」などが代表例です。
| 特徴 | |
| 電気ポットや照明の使用状況をチェックして安否確認が出来ます。 使用履歴を家族へ通知してくれます。 使い慣れた家電に組み込まれているため、抵抗感が少ないです。 | |
| メリット | デメリット |
| 高齢者が意識しすぎずに見守りが出来る 日常の生活を活かした自然な見守りができます。 プライバシーの侵害が少なく済みます。 | 家電を使用しないと異常検知が出来ない。 緊急時の対応には不向き ネット環境や専用機器が必要になる場合もある。 |
見守りサービス・グッズ導入時の注意点
見守りサービス・グッズ導入時の注意点についてまとめておきます。
見守られる側(親)の意見を尊重する

見守りサービス・グッズの導入は見守られる側のプライバシーの侵害に繋がる可能性もあります。
見守られる側が嫌がる可能性も考えられますので、話し合いを重ねた上で導入を検討してください。
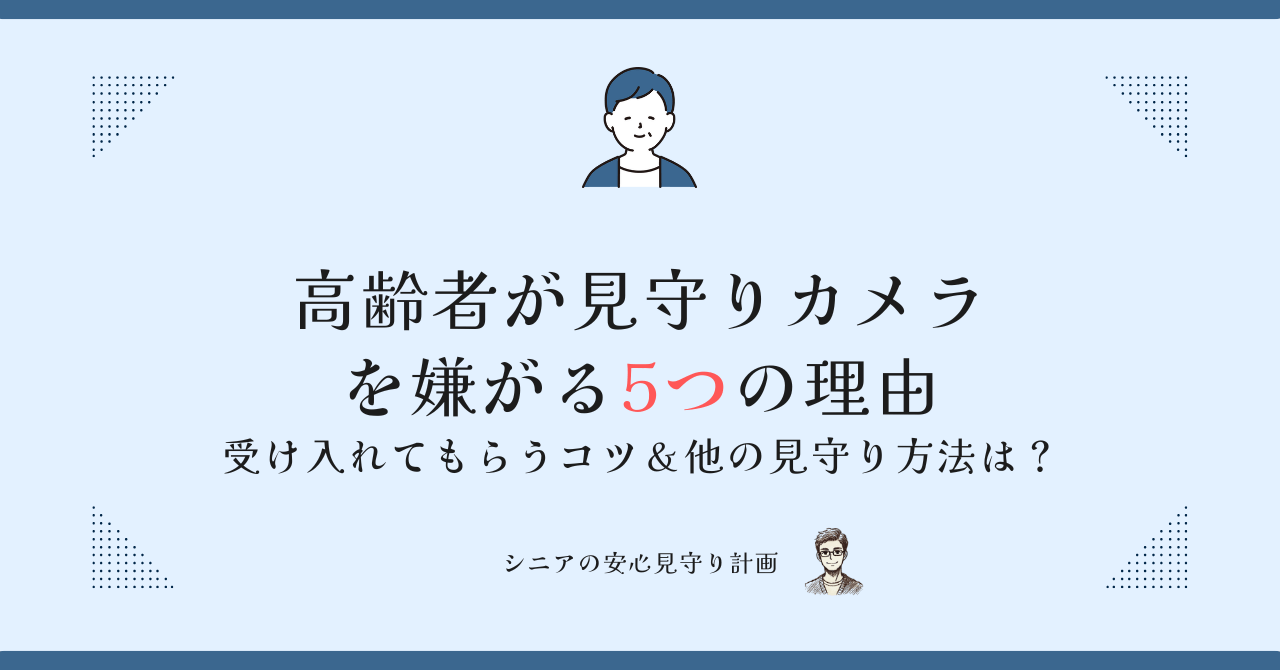
コストと利便性のバランスを考える
8つのサービス・グッズを紹介しましたが、利用料金はサービス・グッズによって様々です。
現在の状況に合わせてコストと利便性のバランスを考えて導入を検討してください。
例えば、下記のようなケースが該当します。
- 今のところ活動的で昔から料理が好きという親御さんの場合は宅食サービスを利用してもあまり意味はなく、むしろ楽しみを奪っていしまう。
- 近くに親戚や頼れる友人がいるのに、緊急時の駆けつけ型サービスを利用してしまうとコスト面がかなり高くなってしまうし、緊急時駆けつけ型のメリットが薄れてしまう
見守る側・見守られる側の求めているニーズをしっかりとすり合わせて最適なサービスを選んでくださいね。
設置・操作が簡単かどうかは事前に確認しておく
専用機器を設置したり、機材を操作する場合は簡単なものかは事前に確認するようにしましょう。
まずは資料請求をすればそのあたりの概要はわかりますし、問い合わせ窓口に電話やメール・チャットなどで相談しておくことも良いかと思います。
まとめ
この記事のまとめ
- 遠方の親の見守り方法として、訪問・同居・見守りサービスの利用などが挙げられる。
- 見守りサービスは訪問型・宅配型・緊急時駆けつけ型など多様な選択肢がある。
- 見守りサービスの導入時には、見守られる側の意見を尊重し、最適なサービス・グッズを選ぶことが大切だと考えられている。
- コスト・利便性・設置の簡単さなどを考慮し、自分の環境に合った見守り方法を検討してください。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
遠方の親の見守りは大きな課題であり、皆様にとっても大きな負担だと思います。
適切な方法を選べば安心して暮らせる環境を整えることができます。
ぜひ、この記事を参考に、最適な見守りサービス・グッズを見つけてください。
少しでも皆様のお力になれれば幸いです。
「シニアの安全見守り計画」では、下記のような方に向けて情報を発信しています。
- 遠方の親が心配だけど、時間がなくて会いに行けない…。
- 最近、体調が良くないって聞いたから心配…。
- 最近元気がないと近所の方に言われた…。
高齢者の見守りサービス・グッズの選び方・口コミ情報などを記事にしています。
あなたの抱えているお悩みの解決に少しでも役立てれば幸いです。
初めての見守りサービス・グッズ選びに迷っている方はぜひ参考にしてみてくださいね!
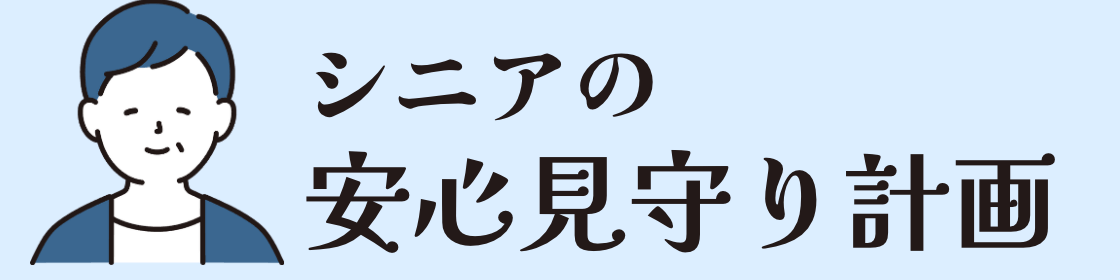
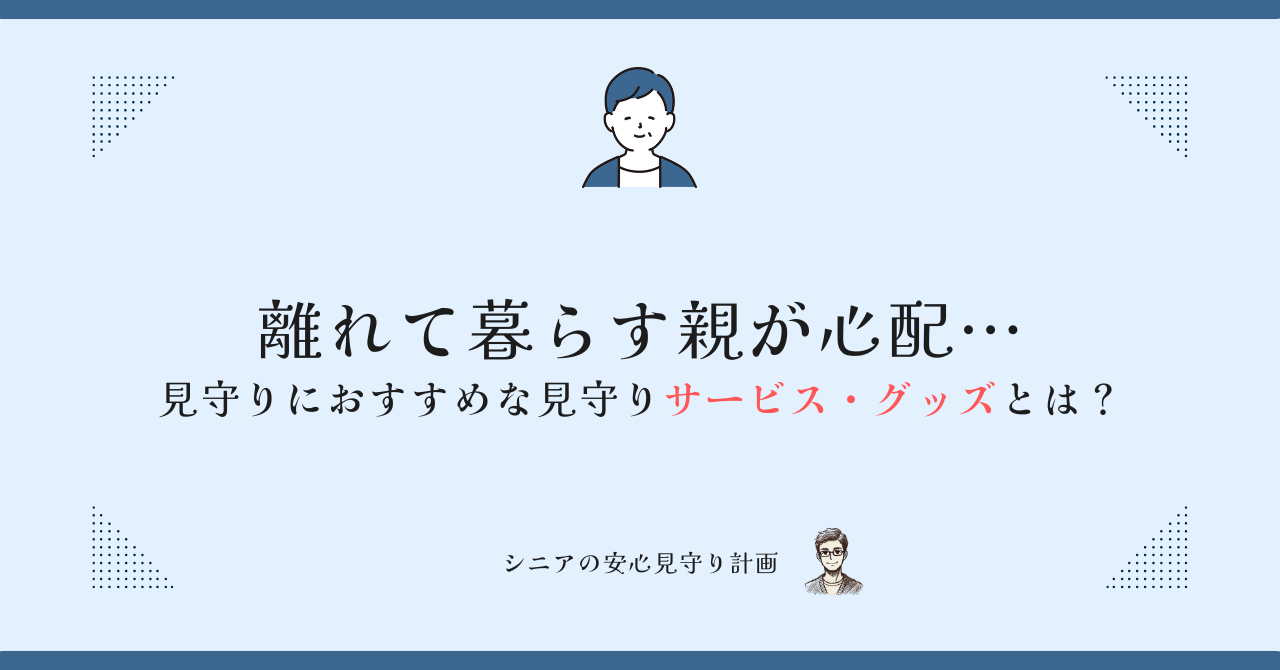
コメント