- 親に見守りカメラの導入を提案しているけど、納得してもらえない…
- カメラ以外に良い方法ってないの…?
- 他の方々はどのように親を説得したの?
あなたはこのような悩みを抱えていませんか?
現在日本では高齢化が進んでおり、「見守り」が重要になってきています。
核家族化も進み、遠方に親が住んでいるというケースも増えてきており、見守りカメラなどの需要も増えてきています。便利な一方で見守られる側から拒否されてしまう場合もありますよね。
実は私も祖父に見守りカメラを提案し、拒否された経験があります。
この記事では高齢者の方見守りカメラを嫌がる5つの理由と、納得してもらうためのコツや他の選択肢を紹介していきます。
見守りカメラは便利な一方でプライバシーの問題などもあります。
見守られる方の意見を尊重しつつ、導入の検討を進めていってもらえれば幸いです。
- 高齢者が見守りカメラを嫌がる理由は、プライバシーや操作面の不安、費用などが考えられる。
- 納得してもらうためのコツとしては、防犯目的で伝える、孫や友人から話す、体験談を交えるなどが有効だと考えられる。
- 見守りカメラ以外にも、センサー型や訪問型などの他の見守り方法も選択肢に入れて話し合うと良い。
- 見守られる側の気持ちを尊重し、両者が納得できる方法を模索することが大事。
この記事を書いた人
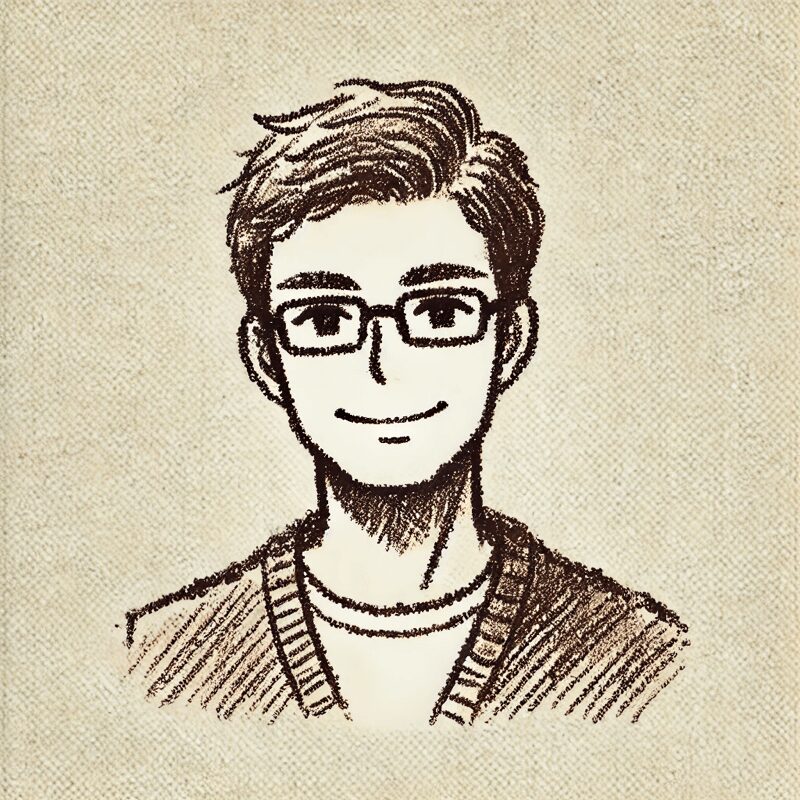
ロキ
30代の会社員。
数年前、祖母が亡くなり一人暮らしになった祖父をサポートをする中で、疲弊する母の姿を見て、「どうにかできないか…」と考えるように。
そこで出会ったのが「高齢者の見守りサービス」でした。
このサービスをもっと多くの人に知ってもらい、「離れていても親を見守る方法」を発信したいと思い、このブログを運営しています。
ぜひ参考にしていただき、少しでもご家族の負担を減らし、安心できる生活につなげていただければ嬉しいです。
一人暮らしの高齢者が増加している現状と見守りの重要性

現在、日本では65歳以上で一人暮らしをする独居老人が増えてきており、2040年には65歳以上の人口のうち男性20.8%、女性24.5%が一人暮らしとなると推測されており、社会全体での支援が求められています。
そんな中で重要になるのが、家族の「見守り」です。
高齢者の一人暮らしは生活意欲の低下、認知症の悪化、孤独死や病気・怪我の際の対応など様々なリスクを伴いますので、家族の見守りが不可欠です。
遠方に住んでいる場合はもちろん、近場に住んでいる場合でも自分の家庭との両立が難しいという方が増えています。
そんなときに役立つのが見守りサービスやグッズです。
民間・自治体で様々なサービスがあり、利用を検討する方も増えてきているとされています。
詳しくは下記の記事をご覧ください。
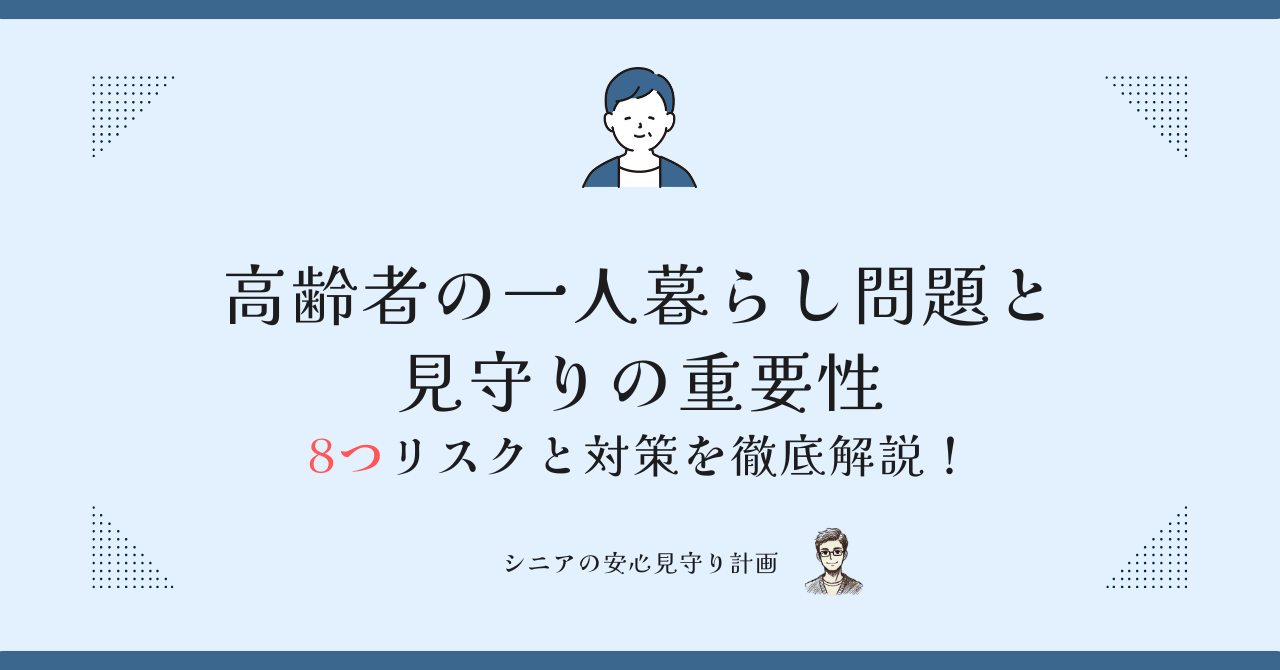
高齢者が「見守りカメラ」を嫌がる5つの理由

高齢者が「見守りカメラ」を嫌がる理由は主に5つあると考えています。
この記事を読んでいる方で導入を相談した際に断られた方も多いのではないでしょうか?
下記のどのパターンに当てはまるか確認してみてください。
監視されているようでプライバシーが侵されると感じる
見守りカメラの導入と聞いて、多くの高齢者が想像されるのがプライバシーの問題なのではないかと思います。
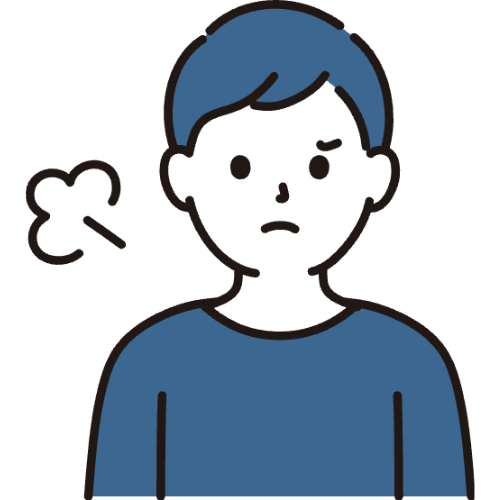
常に見られている気がして嫌だ!
着替えや入浴のときにも気にしないといけないからストレスになる。
あなたの親御さんはこのようなことを感じているのかもしれません。
「常に見られている」と感じていると、それだけで心理的な負担が増す可能性がありますので注意が必要です。
見守られる側の気持ちも尊重しながら検討するようにしましょう。
「まだ自分は一人で大丈夫!」というプライドがある
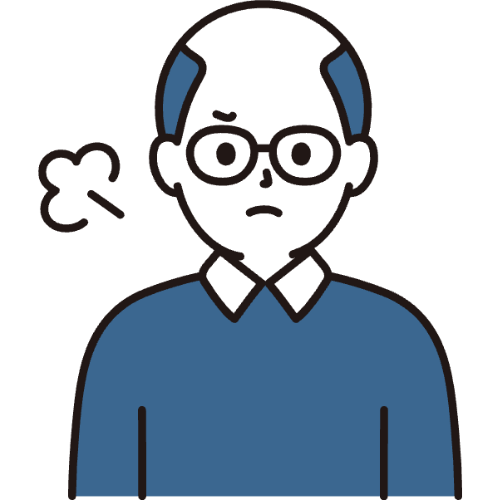
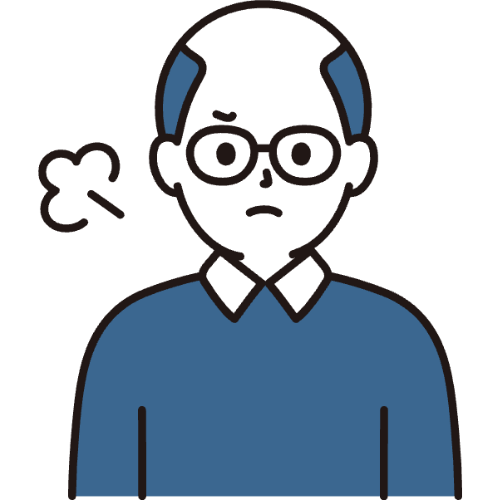
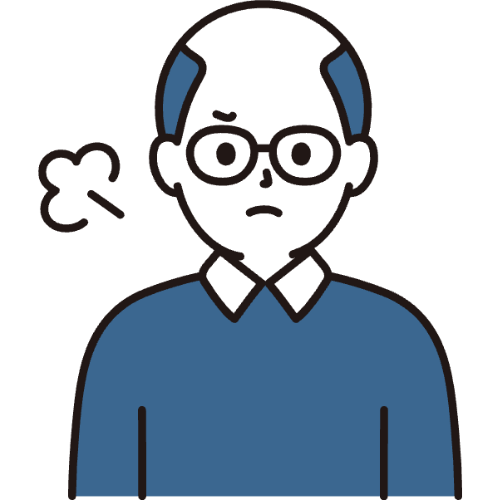
まだ自分は一人で大丈夫だよ!
年寄り扱いするんじゃない!!
こう思われている高齢者の方も一定いらっしゃると思います。
昔から電車やバスで席を譲ったときにこのような返しをする方がいらっしゃいますよね?
それと同じで、自分はまだ一人で生活していける。年寄り扱いされたくないというプライドが働いている可能性があります。
実際に直近体調を崩してしまったり、転倒してしまったりという事故が発生している場合はそのポイントにフォーカスをあてて納得してもらえるか試してみるのが良いかもしれませんね。
機械の操作が難しそうで不安になる
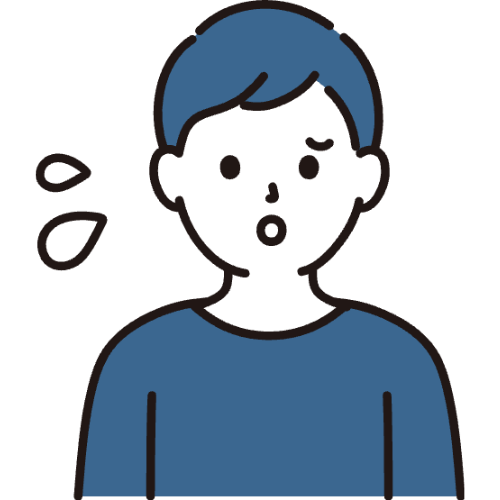
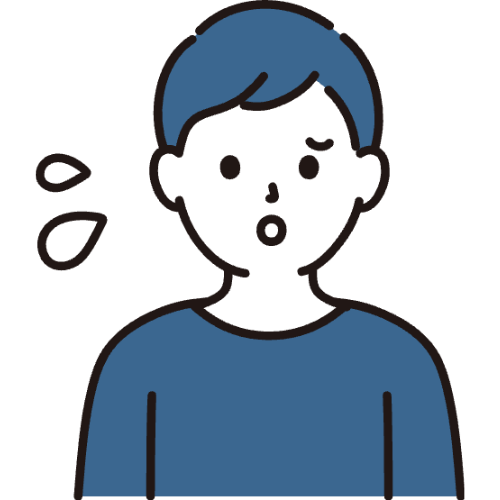
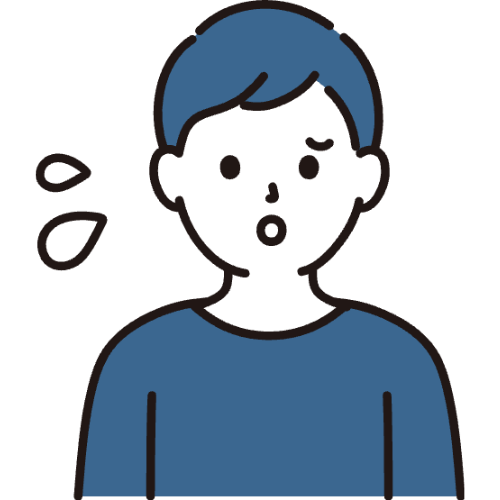
機械が苦手だから導入してもらっても使いこなせないわよ…
スマホでさえ全然使えてないのに、難しそう…
高齢者の方はスマホなどの操作でも一苦労という方が多いと思います。
なんでも操作が難しそうという印象を抱きやすい傾向があるように感じます。
実際に使用している動画などを見たり、お試しキャンペーンや資料請求などをして操作感のイメージ合わせをしてあげることでハードルが下がる可能性があるので、試してみると良いかもしれませんね。
費用がもったいないと感じる
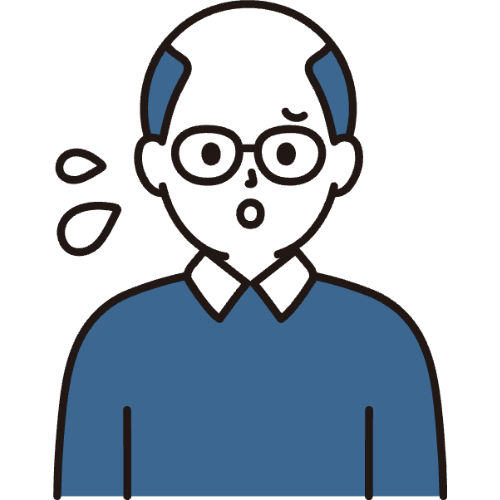
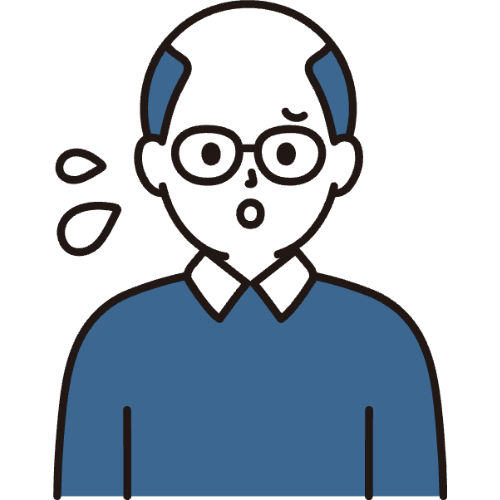
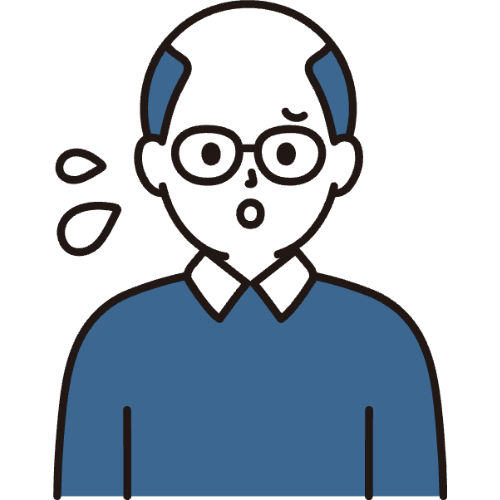
特に問題なく生活出来ているのにお金がもったいない…。
金額に対して得られるメリットに価値をあまり感じない…。
このようなことを思われてる方も多いのではないかと思います。
実際になにも問題が起こっていないのであればお金を捨てているも同然と思ってしまうこともなんとなくわかります。
将来的になにかあったときに役立つということだったり、費用感が安く済む他のサービスも選択肢に入れて提案していくと納得感を得られる可能性が高まるのではないかと思います。
動画の流出や個人情報漏洩の心配



録画された動画はどこかに保存されるの?流出とかの心配はない?
なにか個人情報が写ってしまって、漏洩することはない?
このようなセキュリティ問題に感度が高い方だと、近年の個人情報流出などのニュースを受けて気にされる方もいるのではないかと思います。
セキュリティ対策をしっかりと行うという条件を付けて相談すると良いかもしれません。
高齢者に納得してもらうための具体的なコツ
見守りカメラを嫌がる理由がわかったところで、納得してもらうための具体的なコツをご紹介していきます。
防犯目的として伝える


一番おすすめの方法は見守りカメラを導入する目的は「防犯目的」であることを伝えるということです。
高齢者を狙った空き巣や詐欺などの犯罪は年々増えており、実際に見守りカメラを導入することで対策になるのは間違いありません。
主目的を防犯という観点で伝えることで、抵抗感は減ることが想定されます。
友人や孫から伝えてみる


子どもよりも友人や孫から言われたほうが響くというケースもあります。
実は私もこの方法を試しました。
自分の親では聞く耳を持たなかったので、私から話をしてみることになり、「おじいちゃんのことが心配」ということを伝えてみました。
その場では結果的に納得してもらえなかったんですが、親では聞き出せなかったネックになっていることを聞くことが出来て、話を進展させることは出来ました。皆さんも話し手を変えるということを試してみると話に進展があるかもしれません。
同じ境遇の高齢者の体験談を交えて伝える


出来れば近い存在の方の体験談を出来ると良いと思います。
例えば、御兄弟だったり、近所の同世代の方などの話が良いでしょう。
自分が知っている人も導入しているという話を聞くと、心理的なハードルも下がり、
場合によっては「一度その人の話も聞いてみるか」と心変わりすることがあるかもしれません。
近い存在で見守りカメラの導入をしている方がいない場合は、ネットなどで見守りカメラが役立った場面の体験談などを探して伝えてみると良いかもしれません。
実際に役立つ場面(メリットのある場面)を共通認識として持つことで気持ちが動く可能性が高まるかと思います。
具体的な映像や操作方法を見せる


使用方法に対して不安を覚えている方に有効です。
実際にどのような操作をするのかわかっていないけど、なんとなく難しそうという印象を持っている方が多いので、実際の操作方法を見せましょう。
動画などを送って、「見ておいて」と伝えてもなかなか見てくれないかもしれませんので、一緒に見るのが有効かと思います。
また、もしお試しなどが出来るようであれば実物を使って一緒に操作してみるのが一番良い手段かと思います。
費用を具体的に説明する


お金をかけるのがもったいないと感じている方に有効です。
まず大体いくらくらいだと思っているかにもよるのですが、思っていたよりも安いという実感が得られるのであれば考えが変わる可能性もあります。
まず資料請求をしてみて、費用やサービスの概要などを複数社揃えて情報をまとめて伝えてあげるのが良いかと思います。
他のサービス・グッズを提案してみる。
見守りカメラがどうしても抵抗があるということであれば、他のサービスやグッズなどを提案してみるのも一つの手段です。
他にはどんなものがあるのかわからないという方もいらっしゃると思いますので、まとめておくと下記のようなサービス・グッズがあります。
- 訪問型
- 宅配型
- 電話・アプリ型
- 警備会社・緊急時駆けつけ型
- センサー型
- カメラ型
- ロボット型
- 家電型
例えば、プライバシーの問題が気になるという方であればセンサー型のグッズや電話・アプリ型のサービスを提案したり、食事を作るのが億劫になっているという方であれば宅配型のサービスを提案したりしてみると良いかもしれません。
なにかしらのメリットを感じてもらえれば納得してもらえる可能性は高まると思いますので、見守られる側の状況に合わせて様々な角度から提案できると良いと思います。
家事代行サービスなどを利用して、自分の時間をあける


どうしても見守りサービス・グッズの利用に抵抗があるということであれば、現時点では導入は難しいと思います。
この記事の冒頭にも記載しましたが、導入することによって見守られる側の心理状況や住環境の感じ方が大きく変わりますので本人の意思を尊重してあげることが大事です。
どうしてもご本人が納得されない場合は、見守りをやめるもしくは、どうにか自分が時間を作って見守りをしに行くという選択に限られるかと思います。
そこで家事代行サービスを利用するのがひとつの手段だと考えています。
「第7回全国家庭動向調査」によれば、2022年の各家庭で家事に費やす時間は下記の通りとされています。
| 妻 | 夫 | |
|---|---|---|
| 平日 | 247分(約4時間) | 47分 |
| 休日 | 276分(約4時間半) | 81分(約1時間20分) |
家庭により若干の変動はあるとは思いますが、休日に約4時間半の負担を減らせるのであれば結構な効果なのではないかと思うので、ご興味のある方は検討してみても良いと思います。
見守りカメラの導入についての筆者の体験談
筆者も祖父に見守りカメラの導入を提案して、拒否された経験があります。
祖母が急逝後、祖父の一人暮らしを家族で支えていました。
当初は、幸い実家から祖父の家が車で約1時間ちょっとの距離で通える状態でしたので、定期的に母が訪問をしていました。しかし、仕事との両立で疲弊し始めた母の姿を見て、私自身も見守りサービスを探し始めました。
そこで見つけたのが見守りカメラでした。
当時私は見守られる側がなにか気にするという発想はなく、母にこんなものがあったから祖父に提案してみようと進言しましたが、母は「カメラは気になるんじゃない?」と言いつつも祖父に提案をしました。
すると、母の予想通り抵抗を示して、
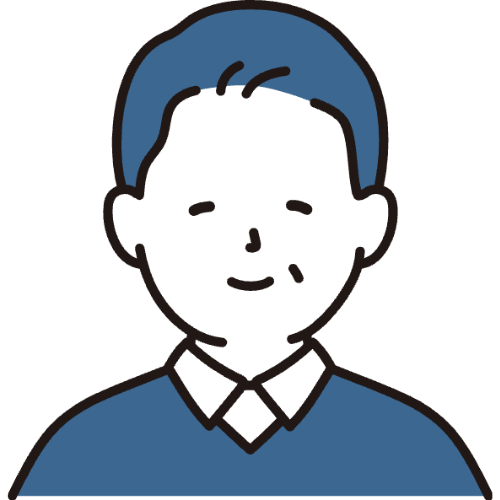
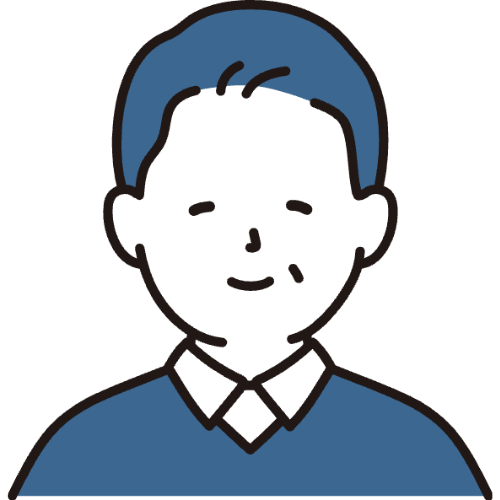
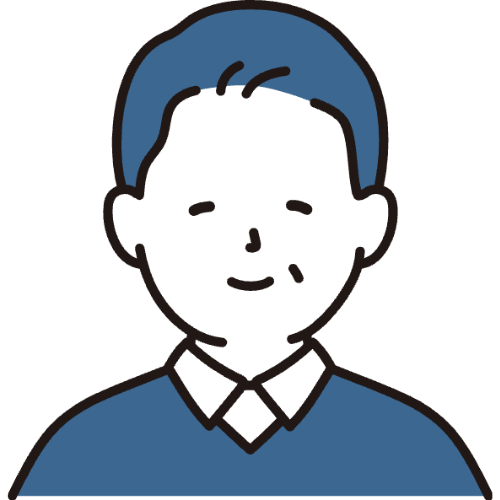
自分はまだ一人で大丈夫
と言って断られてしまいました。
私からも「おじいちゃんのことが心配だから」ということで話をしてみましたが、やはり納得してくれることはありませんでした。ただ、祖父としても
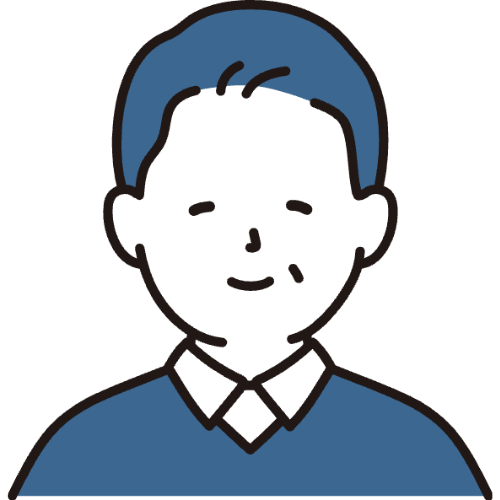
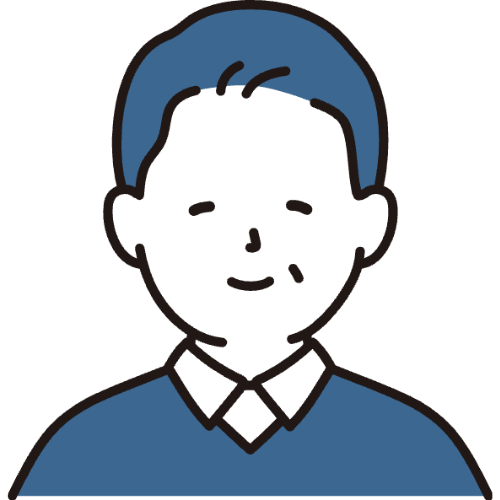
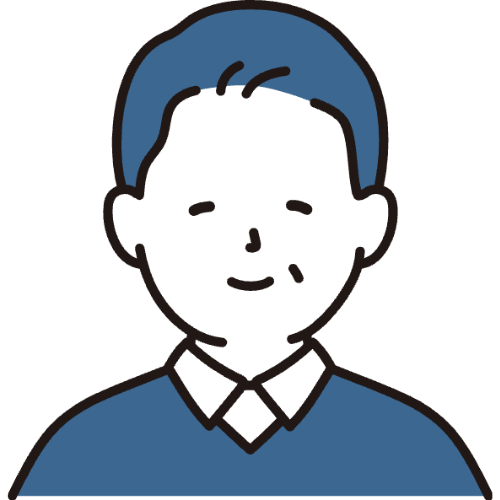
面倒をかけるのは申し訳ないという気持ちは持っていて、見守りのサービスやグッズを利用したほうが母のためにはなると思っている。
ただ、どうしてもカメラは監視されているような気がして抵抗があるんだ…。
という気持ちを聞くことが出来ました。
最終的にはまずはセンサー型のものを導入することで納得してもらうことが出来ました。
この経験から、見守りカメラにこだわりすぎずに、他の選択肢も検討しながら見守られる側の気持ちを尊重しながら決めていくことが重要だと私は考えています。
見守りカメラの導入時期の目安


では、見守りカメラの最適な導入タイミングはいつなのでしょうか?
私が思うのは、「日常のプライバシー」以上に「生命に関わるリスク」が大きくなったときだと思っています。
熱中症や認知症による危険が大きくなった時や、体調を崩しがちになったとき、長時間連絡が取れないなどの問題が具体的になった際には導入するタイミングとしては最適なのではないかと思います。
もちろん、早めに利用できるに越したことはありませんが、見守る側・見守られる側の双方が納得できる方法を他の選択肢も含め話し合って、安心出来る暮らしを実現していきましょう。
まとめ
この記事のまとめ
- 高齢者が見守りカメラを嫌がる理由は、プライバシーや操作面の不安、費用などが考えられる。
- 納得してもらうためのコツとしては、防犯目的で伝える、孫や友人から話す、体験談を交えるなどが有効だと考えられる。
- 見守りカメラ以外にも、センサー型や訪問型などの他の見守り方法も選択肢に入れて話し合うと良い。
- 見守られる側の気持ちを尊重し、両者が納得できる方法を模索することが大事。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
見守りサービスの導入は色々なことを考慮しなければならない難しい問題ですが、様々な選択肢を持って最善な方法を模索していってくださいね。
少しでも皆様のお力になれれば幸いです。
「シニアの安全見守り計画」では、下記のような方に向けて情報を発信しています。
- 遠方の親が心配だけど、時間がなくて会いに行けない…。
- 最近、体調が良くないって聞いたから心配…。
- 最近元気がないと近所の方に言われた…。
高齢者の見守りサービス・グッズの選び方・口コミ情報などを記事にしています。
あなたの抱えているお悩みの解決に少しでも役立てれば幸いです。
初めての見守りサービス・グッズ選びに迷っている方はぜひ参考にしてみてくださいね!
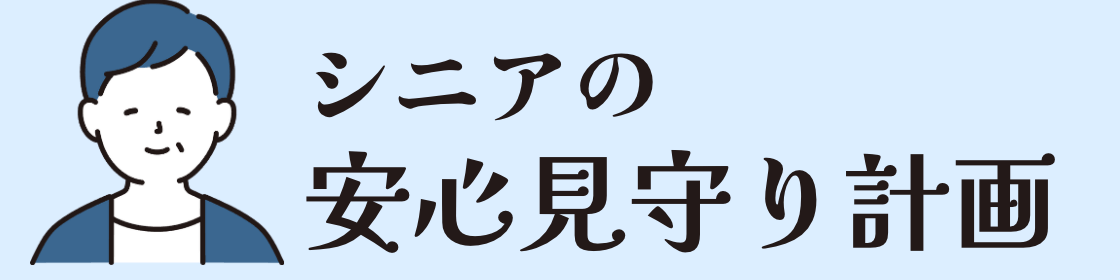
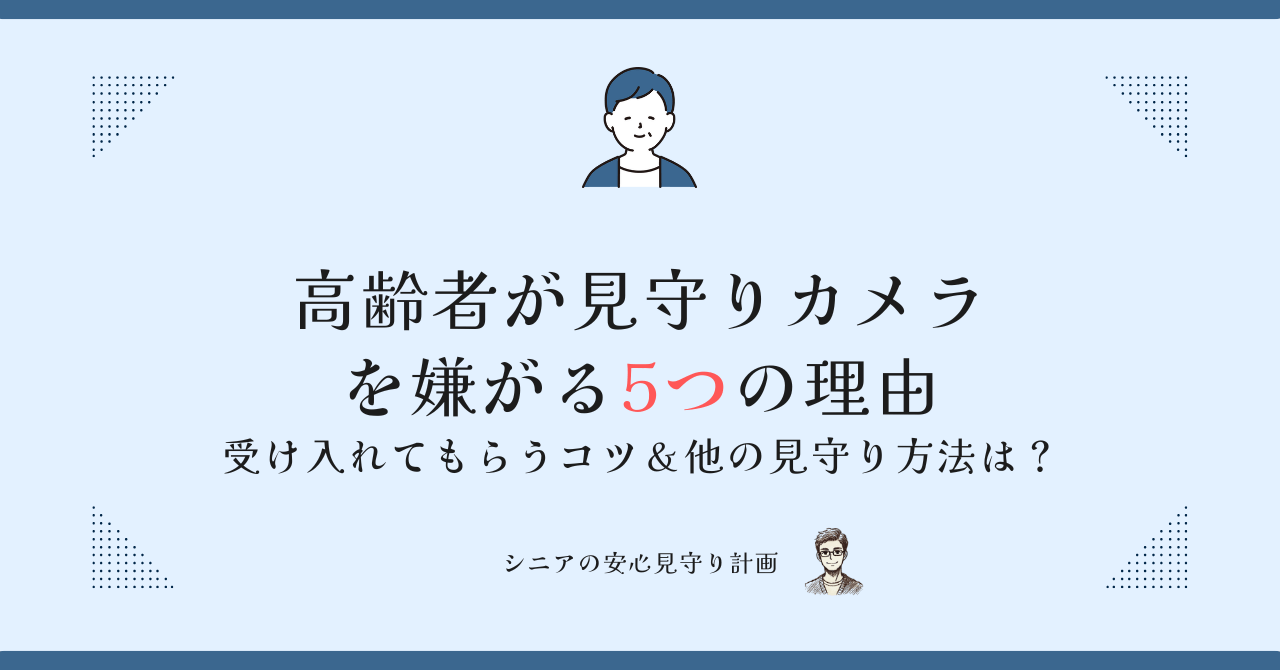
コメント