あなたはこんなお悩みをお持ちではないですか?
- 最近親が一人暮らしになって、どう過ごしているか心配…。
- 仕事が忙しくて親とコミュニケーションが取れていない、元気に過ごしているかな…。
- 近所の人に最近親の元気がないと言われたんだけど、大丈夫なのかな…。
現在日本では高齢化が進んでおり、上記のようなお悩みの方も増えています。
そこで重要になってくるのが「一人暮らしの高齢者の見守り」です。
「見守り」をきちんと行わないと、事件や事故のリスクが高まります。
この記事では「日本の高齢化の実態」と「一人暮らしの高齢者が抱えるリスク」「見守りをはじめとするリスクを回避する方法」を解説します。
見守りの重要性を知り、今後どのような見守り方法を取るかの基礎知識として知っていただきたい情報です。
この記事を通してきちんと理解をし、安心の見守り計画を立てていきましょう。
- 独居老人とは、65歳以上で一人暮らしをする高齢者を指し、年々増加傾向にあります。
2040年には男性20.8%、女性24.5%が一人暮らしになると推測されており、社会全体での支援が求められています。 - 高齢者の一人暮らしは、生活意欲の低下、栄養バランスの悪化、フレイル(虚弱)の進行、孤独死や病気・怪我の際の対応、認知症の悪化、詐欺・犯罪被害の増加など、多くのリスクを伴います。特に、社会との関わりの減少や緊急時の対応困難が問題死されており、地域や家族の支援が不可欠です。
- 高齢者の一人暮らしのリスクを軽減するためには、家族との同居・近居、見守りサービスや介護保険サービスの活用、成年後見制度の活用などが有効です。特に、緊急時に対応できる体制を整え、社会とのつながりを維持することでリスクの軽減につながると考えられます。
この記事を書いた人
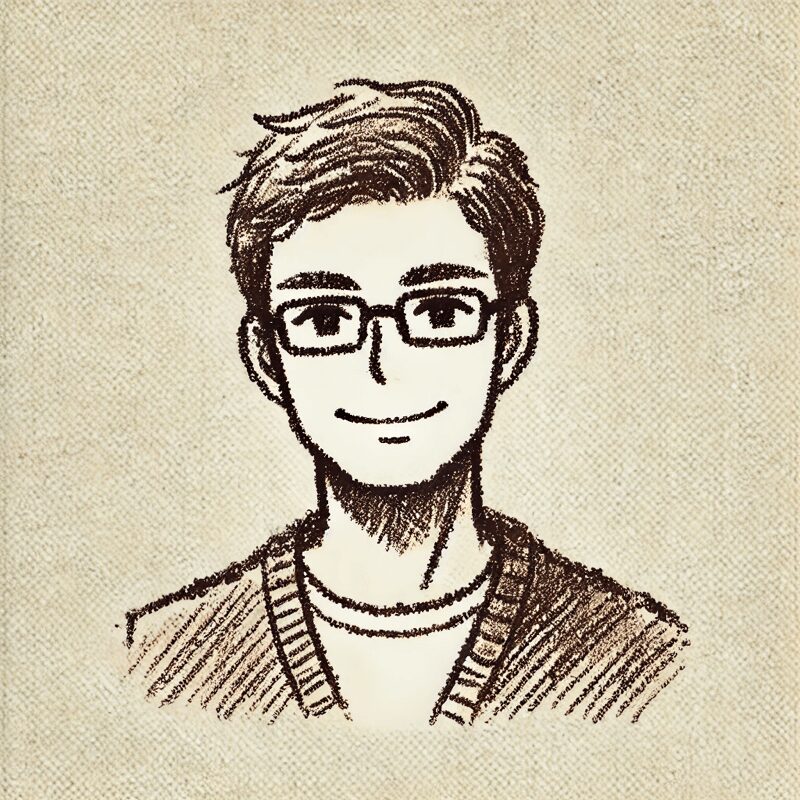
ロキ
30代の会社員。
数年前、祖母が亡くなり一人暮らしになった祖父をサポートをする中で、疲弊する母の姿を見て、「どうにかできないか…」と考えるように。
そこで出会ったのが「高齢者の見守りサービス」でした。
このサービスをもっと多くの人に知ってもらい、「離れていても親を見守る方法」を発信したいと思い、このブログを運営しています。
ぜひ参考にしていただき、少しでもご家族の負担を減らし、安心できる生活につなげていただければ嬉しいです。
近年増加している一人暮らしの高齢者(独居老人)とは?

「独居老人」とは65歳以上の一人暮らしの高齢者を指す言葉です。
未婚の方や、パートナーが死別し一人暮らしになった方を包括的に含んでいます。
近年、一人暮らしの高齢者は年々増加しています。
内閣府の「令和3年版高齢社会白書(全体版)」によると、
一人暮らしの高齢者世帯数・65歳以上人口に占める割合の推移は、下記のように変化してきたとされています。
| 西暦(和暦) | 一人暮らし高齢者世帯数 | 男性の割合 | 女性の割合 |
|---|---|---|---|
| 1980年(昭和55年) | 881世帯 | 4.3% | 11.2% |
| 2000年(平成12年) | 3,032世帯 | 8.0% | 17.9% |
| 2015年(平成27年) | 5,928世帯 | 13.3% | 21.1% |
| 2025年(令和7年) ※予測値 | 7,512世帯 | 16.8% | 23.2% |
| 2040年(令和22年) ※予測値 | 8,963世帯 | 20.8% | 24.5% |
2040年は推定値ではありますが、一人暮らし高齢者世帯数は8,963世帯となり、2000年の2.95倍にまで増加する予測となっています。
(参考元:令和3年版高齢社会白書(全体版))
なぜ一人暮らしの高齢者が増加している?原因を解説
一人暮らしの高齢者世帯数は、なぜ近年増加しているのでしょうか?
前提として、日本の家庭文化が大きく変わったことが要因となっています。
日本では昔は祖父母と同居する3世代家族世帯が多くありましたが、核家族化が進み、現代では親と子供が同居するスタイルの世帯は減ってきています。
このような時代背景と合わせて、高齢者がこれから紹介するような心理を抱えて一人暮らしを選択することが増えてきているようです。
頼れる人が身近にいない

少子化や核家族化に伴い、「身近に家族がいない」という環境の高齢者が増えています。
元々夫婦で生活をしていたものの、パートナーに先立たれ頼れる親族も近くにいないため、
そのまま一人暮らしをするという選択を取っている高齢者も多いようです。
家族に迷惑をかけたくない

内閣府の「平成27年版高齢社会白書(概要版)」の将来の準備に関する意識調査によると、
病気などのときに世話を頼みたいと考える相手について、子どもがいる男女が「子」と回答した割合は、
男性で58.2%、女性で41.0%と約半数に留まっていることがわかりました。
このことからそもそも家族に迷惑をかけたくないと感じている高齢者は多く、
同居をするとなると迷惑・世話をかけてしまうと感じることが理由で一人暮らしを選択している高齢者も多いと考えられます。
(参考元:平成27年版高齢社会白書(概要版))
現在の暮らしに満足している

内閣府が行った「平成28年 高齢者の経済・生活環境に関する調査結果(全体版)」によると、
「現在の経済的な暮らし向きについてどのように考えているか」という質問に対して、下記の回答結果が得られています。
上記の回答結果から、約65%の高齢者は、経済的な不安は感じずに生活に満足していることがわかります。
このような現在の生活に対しての満足から一人暮らしを選択している方も多いと考えられます。
(参考元:平成28年 高齢者の経済・生活環境に関する調査結果(全体版))
生活環境を変えるのに抵抗がある

内閣府が行った「平成28年 高齢者の経済・生活環境に関する調査結果(全体版)」によると、
全体の約88%が持ち家で生活をしているということがわかります。
持ち家ですと、長く住んでいる可能性が高いですし、生活環境を変えるとリフォームや売却などの手間が発生する可能性が高いです。
そういった環境の変化を避け、一人暮らしを選択している方もいらっしゃると考えられます。
(参考元:平成28年 高齢者の経済・生活環境に関する調査結果(全体版))
高齢者の一人暮らしは危険?想定されるリスクとは
高齢者の一人暮らしは様々なリスクを伴います。
想定されるリスクについていくつか紹介していきます。
生活意欲の低下

内閣府が公開している「平成23年度 高齢者の経済生活に関する意識調査結果(全体像)」によると、
高齢者の会話の頻度(電話やEメールも含む)は、単身世帯以外の回答者は毎日が9割だったのに対し、
単身世帯では毎日と回答したのが約75%、「2〜3日に1回」が14.8%という結果でした
このことからも一人暮らしをすることで社会との関わりが少なることが想定されます。
社会との関わりが少ないと、生きがいを感じにくく、家事や身の回りのことが疎かになりがちです。
外出頻度が減ることで生活リズムが崩れ、他人との交流機会が減ることにも繋がるので悪循環に陥りやすくなると考えられています。
栄養バランスの悪化

自炊が億劫になることで簡易的な食事やインスタント食品に偏りがちになります。
食生活の変化によって高血圧やフレイル(虚弱)につながりやすくなると考えられています。
フレイル(虚弱)の進行

外出の機会が減ることによって、体力・筋力が低下しやすくなります。
それにより要介護状態に発展してしまうリスクがあります。
精神的な不安・孤独を感じる

厚生労働省の公開している「高齢期に増加する生活習慣病の医療費」によると、
「年をとると誰でもうつっぽくなる」と言われることがありますが、重要な他者の死別や身近な人が生命の危機にさらされるなどの重大なライフイベントや、慢性的なストレスによりうつ病を発症しやすくなるとされています。
特に一人では精神的な不安を感じやすい環境なので、注意が必要です。
(参考元:厚生労働省「高齢期に増加する生活習慣病の医療費」)
孤独死、健康や病気の対応
急な病気や怪我の際に助けを求められず、適切なタイミングでケアが出来ないリスクがあります。
最悪の場合、孤独死につながることも考えられますので注意が必要です。
孤独死の数は近年、高齢者人口の増加に合わせて増えてきています。
東京都保健医療局の情報によると、2021年(令和3年)に東京都で発生した孤独死の事例数は3,963件でした。
2016年(平成28年)は3,175件でしたので、5年間で788件、約20%増加していることがわかります。
(参考元:東京都保健医療局「東京都監察医務院で取り扱った自宅住居でなくなった単身世帯の者の統計」)
認知症の進行
本人は自覚がないまま認知症が進行してしまい、服薬・金銭管理の問題や、火の不始末などのリスクにつながるので注意が必要です。
認知症の具体的な症状を下記に引用しておきますが、一人暮らしでは様々なリスクにつながるような症状が多いです。
認知症の中核症状の例として、次のようなものがあります。
もの忘れ(記憶障害)
数分前、数時間前の出来事をすぐ忘れる
同じことを何度も言う・聞く
しまい忘れや置き忘れが増えて、いつも探し物をしている
約束を忘れる
昔から知っている物や人の名前が出てこない
同じものを何個も買ってくる
時間・場所がわからなくなる(見当識障害)
日付や曜日がわからなくなる
慣れた道で迷うことがある
出来事の前後関係がわからなくなる
理解力・判断力が低下する
手続きや貯金の出し入れができなくなる
状況や説明が理解できなくなる、テレビ番組の内容が理解できなくなる
運転などのミスが多くなる
仕事や家事・趣味、身の回りのことができなくなる
仕事や家事・趣味の段取りが悪くなる、時間がかかるようになる
調理の味付けを間違える、掃除や洗濯がきちんとできなくなる
身だしなみを構わなくなる、季節に合った服装を選ぶことができなくなる
食べこぼしが増える
洗面や入浴の仕方がわからなくなる
失禁が増える
行動・心理症状(BPSD)
認知症に伴う行動・心理症状(BPSD)には、次のようなものがあります。
不安、一人になると怖がったり寂しがったりする
憂うつでふさぎこむ、何をするのも億劫がる、趣味や好きなテレビ番組に興味を示さなくなる
怒りっぽくなる、イライラ、些細なことで腹を立てる
誰もいないのに、誰かがいると主張する(幻視)
自分のものを誰かに盗まれたと疑う(もの盗られ妄想)
目的を持って外出しても途中で忘れてしまい帰れなくなってしまう
軽度認知障害(MCI)のサイン・症状
認知症のサインまではいかなくても、少しだけ加齢によるもの忘れが強いと感じたら、MCIの可能性も考えられます。
MCIの特徴としては、下記の3つが挙げられます。以前と比べてもの忘れなどの認知機能の低下がある、本人が自覚している、または家族等によって気づかれる
もの忘れが多いという自覚がある
日常生活にはそれほど大きな支障はきたしていない
引用元:国立精神・神経医療研究センター 精神保健研究所「こころの情報サイト_認知症」
詐欺や犯罪被害に巻き込まれる

還付金詐欺、架空請求、悪質リフォーム、定期購入トラブルなどを始めた詐欺や犯罪は後を絶ちませんが、中でも高齢者を狙った詐欺や犯罪は近年ますます増えてきてます。
警視庁が発表している「特殊詐欺の認知・検挙状況等について(確定値版)」によると、2022年(令和4年)の特殊詐欺の認知件数は17,570件で前年比+3,072件となっています。
高齢者が被害にあった詐欺の認知件数は15,114件となっており、法人被害を除いた総認知件数に占める割合は約86%にも及んでいます。
(参考元:警視庁「特殊詐欺の認知・検挙状況等について(確定値版)」)
自然災害への対処が困難

近年、異常気象の影響で全国各地で大雨による洪水や地震、山火事などが増えているといわれています。
高齢者が一人で暮らしていると避難が必要な場合でも、自力で対処できずに適切なタイミングで避難ができない恐れがあります。
自然災害だけではなく、火災などの場合も同様です。
一人暮らしの高齢者のリスクを軽減する方法と対策
ここまでで述べてきたようなリスクにはどのように対応すればよいのでしょうか?
代表的な対処方法について紹介していきます。
家族と同居、もしくは近居する

一番良いのはご家族と同居、もしくは近居することです。
ただ、受け入れる側も家族の協力が必要ですし、生活負担も増加します。
高齢者側も迷惑をかけたくないなどの心理的な懸念がある可能性もありますので、家族できちんと話し合いをして決めていくことが重要です。
同居はしないにしても、近居をすることによって不測の事態があった場合にすぐに駆けつけられる体制は整うので、
良い方法だと考えられています。
近居の場合はこのあとに紹介する見守りサービスやグッズなども併用しながら見守りをしていくことが重要です。
見守りサービス・グッズを利用する

見守りサービスやグッズを利用するのも一つの手段だと思います。
見守りサービスについては民間の会社が運営しているものや自治体のサービスなどもあります。
例を挙げると、緊急時に駆けつけてくれるサービスや、定期的な訪問、食事などを宅配してくれるサービスなどがあります。
見守りグッズは、見守りカメラなどが代表的なものですが、他にもセンサーだったり、ロボットのようなものがあります。
見守りサービス・グッズを利用して離れて暮らしていてもお互い安心の感の高い状況を作っていくことで、
双方にとって生活の満足度を上げていくことにも繋がります。
見守りサービス・グッズは他の方法と併用して使うことによって、より万全な見守り体制を築くことにも繋がりますので利用をおすすめします。
介護保険サービスを利用する

要介護認定を受けて、訪問介護やデイサービスを利用するのも一つの手段です。
特に訪問介護では、自分の住み慣れた家で過ごすことができ、「介護職員初任者研修」などの介護についての資格を持ったヘルパーさんにケアをしてもらうことが出来るので安心できます。
デイサービスに通うことによってコミュニケーションの総量を増やすことが出来るのも魅力ですね。
ただ、どうしてもそういった施設には通いたくないという高齢者の方もいらっしゃるので、
御本人のご意向を尊重したうえでケアしていくことが大事になります。
成年後見人制度を活用する
成年後見人制度とは、下記のような制度です。
自分ひとりでは わからない!?
そんな時でも 安心して くらせるために。 知的障害・精神障害・認知症などによって
引用元:厚生労働省「成年後見はやわかり」
ひとりで決めることに不安や心配な人が いろいろな契約や手続をする際に
同じ地域に暮らすさまざまな人がつながって
ご本人の思いを分かち合い、いっしょに考え お手伝いする制度です。
認知症や判断能力の低下に備えて、後見人をあらかじめ選んでおくこともトラブル防止の観点では大事になります。
財産管理や医療・介護の契約などを適切に行えるように準備しておきましょう。
まとめ
この記事のまとめ
- 独居老人とは、65歳以上で一人暮らしをする高齢者を指し、年々増加傾向にあります。
2040年には男性20.8%、女性24.5%が一人暮らしになると推測されており、社会全体での支援が求められています。 - 高齢者の一人暮らしは、生活意欲の低下、栄養バランスの悪化、フレイル(虚弱)の進行、孤独死や病気・怪我の際の対応、認知症の悪化、詐欺・犯罪被害の増加など、多くのリスクを伴います。特に、社会との関わりの減少や緊急時の対応困難が問題視されており、地域や家族の支援が不可欠です。
- 高齢者の一人暮らしのリスクを軽減するためには、家族との同居・近居、見守りサービスや介護保険サービスの活用、成年後見制度の活用などが有効です。特に、緊急時に対応できる体制を整え、社会とのつながりを維持することでリスクの軽減につながると考えられます。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
高齢者の見守りの重要性について、きちんと理解し、ご家族の皆さんが安心して幸せな生活を送れるように計画を立てていってくださいね!
「シニアの安全見守り計画」では、下記のような方に向けて情報を発信しています。
- 遠方の親が心配だけど、時間がなくて会いに行けない…。
- 最近、体調が良くないって聞いたから心配…。
- 最近元気がないと近所の方に言われた…。
高齢者の見守りサービス・グッズの選び方・口コミ情報などを記事にしています。
あなたの抱えているお悩みの解決に少しでも役立てれば幸いです。
初めての見守りサービス・グッズ選びに迷っている方はぜひ参考にしてみてくださいね!
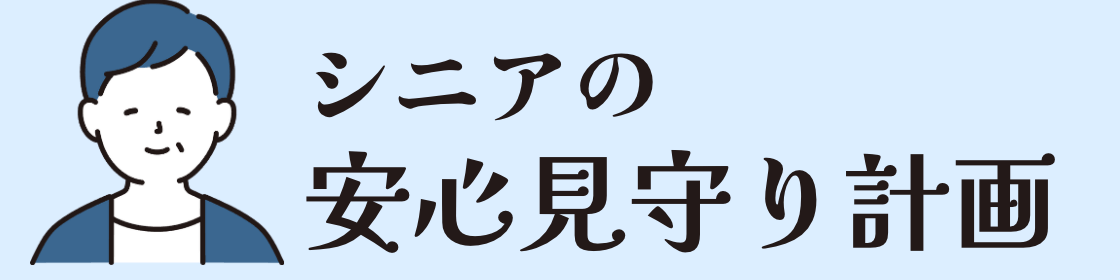
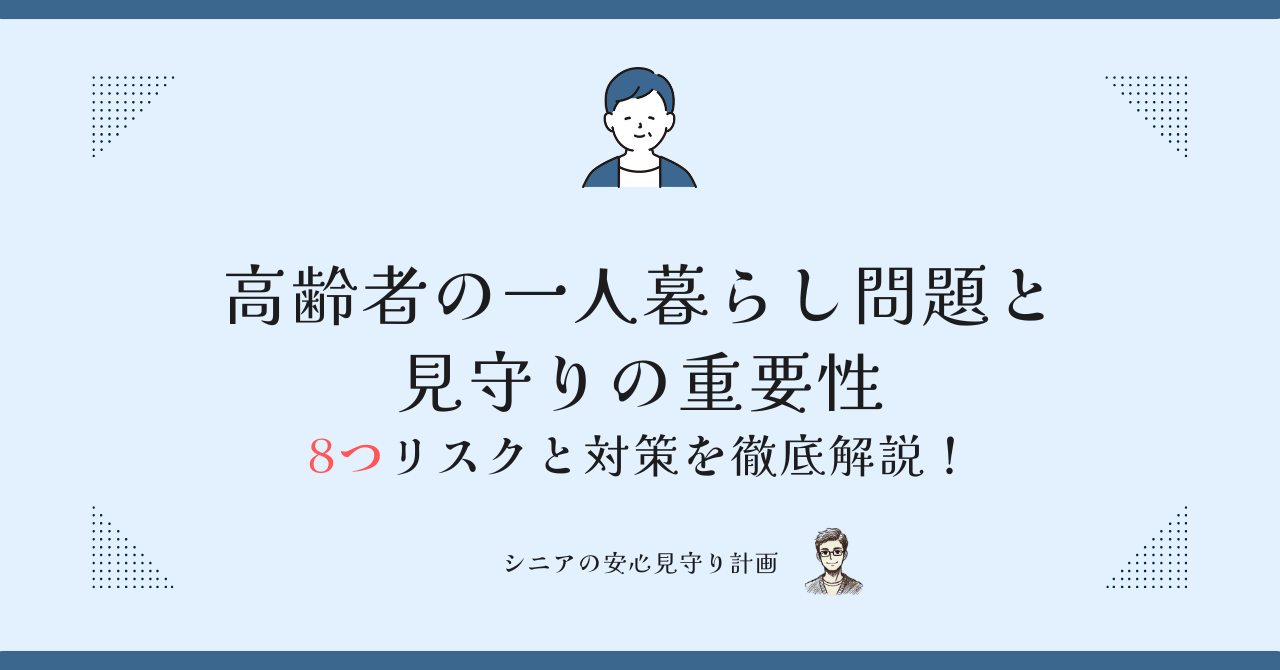
コメント